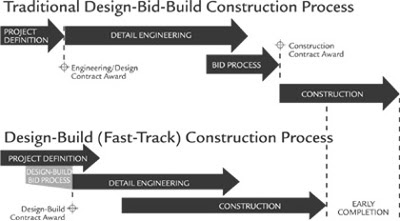一家族しか住むことを認められていないという話をご紹介しました。
今回はその話をもう少し掘り下げ、ゾーニングの話をしたいと思います。
ゾーニングとは
 | |
| ホノルルのゾーニングマップ |
ゾーニングとはホノルル市及びハワイ州が定めている土地の用途区分です。
例えば、住宅街の真ん中にナイトクラブや、工場が出来たら困りますよね。
毎晩騒音や空気汚染に悩まされることになってしまいます。
そのようなことを避けるために、地域別に建物の用途を制限しているのがゾーニングです。
ゾーニングは大まかに建物の用途や建物の高さ及び密度を制限します。
住宅街のゾーニング
住宅街のゾーニングは最も厳しいものになっています。
妨げなく就寝できるよう、最も静かな環境を守る必要があるからです。
この住宅街のゾーニングは、R3.5、R5、R7.5、R10、R20とあります。
RはResidentialを意味しています。後ろの数字は敷地の最低面積を表しています。
R5であれば、5,000 sqft(平方フィート)以上の敷地でなければならないという意味です。
ただ、5,000 sqftよりも多少小さい敷地もすでに存在している場合には特に問題ではありません。
ここで、もしR5のゾーニングで10,000 sqftもの土地を所有しているとすると、
規定の倍の広さとなりますので、同じ敷地に2軒の家を建てることができ、
個々の家に合法的にキッチンやランドリーを設置することができます。
基本的には上記のような考え方なのですが、その他にもいくつか制限があり、
同じ敷地内において複数軒の家を建てることができない場合もありますので、
まずは建築士に相談をしてみることをお勧めします。
ゾーニングの変更
市や州がゾーニングを変更することは決して珍しいことではありません。
したがって、所有している土地のゾーニングが変更すれば、
建設できる範囲やその種類なども変わってきます。
例えば80年代中盤頃に、海岸沿いのセットバックは40フィートと定められ、
海岸沿線から40フィートのところまで建物を建設することができなくなりました。
その変更以前に建てられた建物で、40フィートより海岸に近い建物はたくさんありますが、
それらは合法になります。
このように、ゾーニングが変更された場合には、
通常それ以前の建物は現状維持を認められますが、
建て直しはもちろん、改築や増築・減築の際に、
新しい法律が適用されるケースもありますので十分に注意が必要です。